| 2025/11/25 16:03 |
[PR] |
| 2013/02/04 11:35 |
オーディオニルバーナ 脱ダンボール その2 |
みなさんこんにちは。
サムライジャパンでございます。
前回お話しましたように、うちのAudioNirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジユニットは、今までの惨たらしい段ボールから脱却し、ついに念願の木製エンクロージャーへと入れ替える事が決まりました。

先回もお話したように、使用するエンクロージャーは、EV製のPA用のスピーカーシステムのエンクロージャーで、15インチウーハーとホーンドライバーが入っていた、2ウエイのエンクロージャーです。
概算の内容積を計算すると、およそ140リットルほどで、これに装着するAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOはご覧のように6.5インチ(16センチ)ユニットですので、コンパクトシステムに用いられるサイズのユニットという事を考えれば、一般的にオーバーキャパシティーになるのでしょう。

もうかなり前の話ですが、以前まで鳴らしていたALTEC 515-16Cを入れていた、アピトン合板製の強固な230リットルのエンクロージャーに、ダイヤトーンのP610の初期型を入れて鳴らした事があります。
バスレフの指定箱サイズでいえば、45~70リットルサイズまでが許容サイズになり、このサイズのエンクロージャーでは非常にすばらしい音が聞けます。
一方コンパクトな箱に押し込むと、P610はかなり苦しそうに鳴ってしまい、正直聞いていてあまり気分のいいものではありません。
そんな事で230リットルのエンクロージャーを試したのですが、さすがにこれも無理でしたね。
ローエンドがだら下がりの傾向になり、平面バッフル的な音になるものの、箱で囲われた影響からか、伸び伸びとした鳴り方も影を潜めてしまい、これはこれでつまらない音になってしまいました。
そのような意味ではユニットには最適なサイズのエンクロージャーが必要なのですけど、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOにはどの程度がベストなのかといえば、これがまた許容範囲がかなり広いのです。
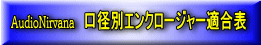
適合表をご覧いただければおわかりですが、最小の12リッターから最大では300リッターまで許容範囲に広いユニットでもあります。
ただしさすがに12リッターは、AV用などのサブ用としての使用が前提になるでしょうから、実質的に実用的になるのは25リッター以上となるでしょう。
25リッタークラスといえば、16センチのコンパクトモニターとしては定番的なサイズで、一般的に一番多く見られるサイズでもありますが、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOにはどうかといえば、正直あまりお勧めできるサイズではありません。
このサイズに入れるユニットとしては、振動系が比較的重めで低能率のユニットを、容積の小ささを利用してダンピングを効かせる鳴らし方のほうが相性がよく、パワフルな磁気回路でで軽量振動系を駆動するAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOの場合、逆に内容積に小ささが振動系の動きを制限してしまいやすく、これまたふん詰まりなつまらない傾向になりやすいのです。
実際段ボール箱での実験を繰り返してみると、容積80リットル以上のほうが相性がいいようです。
低域のレンジの拡大はもちろん、その低域の音の出方も容量の大きいほうが切れもよく、スケール感の大きな音に変化してきました。
そのようなわけで、実際のところ160リットル~あたりに入れたいのが本音でしたが、EVのPA用の容積が140リットル程度であり、これなら十分いけそうだと感じたので入れる事にしたのです。
それに箱を一から自作するのに比べ、バッフル板だけの加工ですむのですから、工作難易度も非常に低く、また作業スペースも狭くても可能ですので、狭いアパートの一室でも十分加工作業が可能ですね。
という事で早速加工する事としました。

エンクロージャーの材質はパーチクルボードのようで、昔はよくメーカー製のエンクロージャーに使われていた材質のようですね。
板厚は18ミリ~21ミリ程度の標準的な厚さで、補強も申し訳程度にあるだけで、音響的に研究されているというものではありません。
本当であれば木枠で鳥かごのように細かい補強材を入れる事により、各板面の共振モードをコントロールする事ができますので、多少板材が粗悪でも意外と響きのいいエンクロージャーに仕上げるのは難しくありません。
でも今回はとにかく手軽な鳴らし方の提案という事ですので、補強枠などの話はまた時を改めてお話をしていきたいと思います。
さてそこでバッフル板をどうするかという事ですが、ご覧のようにバッフル面いっぱいに以前ユニットが取り付けられていたねじ穴がたくさんありますので、今回はまずこれによって板を取り付けることにしました。
次に悩むのがバッフル板の材質選定です。
自作派の方には圧倒的な人気と支持のある、音質的に良いフィンランドパーチやアピトン合板などもありますが、箱全体だと材料費がかかさむものの、バッフル板だけの使用であればそれほど高額ではありません。
でも今回はそれはまたのお楽しみにします。
という事で、近所のホームセンターへ板材の買出しに出かけてみました。
自作派の方によく利用されるラワン合板やシナ合板も考えましたが、それではありきたりでつまらない話です。
コスト優先でMDF材も候補になりましたが、音質との兼ね合いでコストパフォーマンスは高いものの、それでもちょっと面白くありませんね。
見た目の綺麗さでパイン集積材や竹の集積材もいいとは思ったのですが、どうせならマニアが敬遠する材質を使用してみようと思ったのです。
そこで目に入ったのが、なんだかわけのわからない集積材です。
バルサほどではありませんが、非常に軽く柔らかめの材質です。
高硬度、高密度 高比重の三高の材質を望むマニアが多い中、あえて軟質、低密度 低比重のへっぽこ木材を使用してみる事にしました。
どのような材質かといえば、通販などで売っている安物の出来の悪い桐タンスに使われているような材質といえばお分かりでしょうか。

今まで段ボール箱で鳴らしてきた経験があるため、こんな低比重な軟質な材料でも十分勝算があっての話です。
それにこのくらい大きなハンデを与えないと、世の中にある高級ブランドのシステムより良く鳴ってしまいますから・・・
という事で今回はここまで。
次回はいよいよ完成風景についてご報告いたしますね。
サムライジャパンでございます。
前回お話しましたように、うちのAudioNirvana(オーディオニルバーナ)のフルレンジユニットは、今までの惨たらしい段ボールから脱却し、ついに念願の木製エンクロージャーへと入れ替える事が決まりました。

先回もお話したように、使用するエンクロージャーは、EV製のPA用のスピーカーシステムのエンクロージャーで、15インチウーハーとホーンドライバーが入っていた、2ウエイのエンクロージャーです。
概算の内容積を計算すると、およそ140リットルほどで、これに装着するAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOはご覧のように6.5インチ(16センチ)ユニットですので、コンパクトシステムに用いられるサイズのユニットという事を考えれば、一般的にオーバーキャパシティーになるのでしょう。

もうかなり前の話ですが、以前まで鳴らしていたALTEC 515-16Cを入れていた、アピトン合板製の強固な230リットルのエンクロージャーに、ダイヤトーンのP610の初期型を入れて鳴らした事があります。
バスレフの指定箱サイズでいえば、45~70リットルサイズまでが許容サイズになり、このサイズのエンクロージャーでは非常にすばらしい音が聞けます。
一方コンパクトな箱に押し込むと、P610はかなり苦しそうに鳴ってしまい、正直聞いていてあまり気分のいいものではありません。
そんな事で230リットルのエンクロージャーを試したのですが、さすがにこれも無理でしたね。
ローエンドがだら下がりの傾向になり、平面バッフル的な音になるものの、箱で囲われた影響からか、伸び伸びとした鳴り方も影を潜めてしまい、これはこれでつまらない音になってしまいました。
そのような意味ではユニットには最適なサイズのエンクロージャーが必要なのですけど、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOにはどの程度がベストなのかといえば、これがまた許容範囲がかなり広いのです。
適合表をご覧いただければおわかりですが、最小の12リッターから最大では300リッターまで許容範囲に広いユニットでもあります。
ただしさすがに12リッターは、AV用などのサブ用としての使用が前提になるでしょうから、実質的に実用的になるのは25リッター以上となるでしょう。
25リッタークラスといえば、16センチのコンパクトモニターとしては定番的なサイズで、一般的に一番多く見られるサイズでもありますが、Audio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOにはどうかといえば、正直あまりお勧めできるサイズではありません。
このサイズに入れるユニットとしては、振動系が比較的重めで低能率のユニットを、容積の小ささを利用してダンピングを効かせる鳴らし方のほうが相性がよく、パワフルな磁気回路でで軽量振動系を駆動するAudio Nirvana 'Super 6.5 ALNICOの場合、逆に内容積に小ささが振動系の動きを制限してしまいやすく、これまたふん詰まりなつまらない傾向になりやすいのです。
実際段ボール箱での実験を繰り返してみると、容積80リットル以上のほうが相性がいいようです。
低域のレンジの拡大はもちろん、その低域の音の出方も容量の大きいほうが切れもよく、スケール感の大きな音に変化してきました。
そのようなわけで、実際のところ160リットル~あたりに入れたいのが本音でしたが、EVのPA用の容積が140リットル程度であり、これなら十分いけそうだと感じたので入れる事にしたのです。
それに箱を一から自作するのに比べ、バッフル板だけの加工ですむのですから、工作難易度も非常に低く、また作業スペースも狭くても可能ですので、狭いアパートの一室でも十分加工作業が可能ですね。
という事で早速加工する事としました。

エンクロージャーの材質はパーチクルボードのようで、昔はよくメーカー製のエンクロージャーに使われていた材質のようですね。
板厚は18ミリ~21ミリ程度の標準的な厚さで、補強も申し訳程度にあるだけで、音響的に研究されているというものではありません。
本当であれば木枠で鳥かごのように細かい補強材を入れる事により、各板面の共振モードをコントロールする事ができますので、多少板材が粗悪でも意外と響きのいいエンクロージャーに仕上げるのは難しくありません。
でも今回はとにかく手軽な鳴らし方の提案という事ですので、補強枠などの話はまた時を改めてお話をしていきたいと思います。
さてそこでバッフル板をどうするかという事ですが、ご覧のようにバッフル面いっぱいに以前ユニットが取り付けられていたねじ穴がたくさんありますので、今回はまずこれによって板を取り付けることにしました。
次に悩むのがバッフル板の材質選定です。
自作派の方には圧倒的な人気と支持のある、音質的に良いフィンランドパーチやアピトン合板などもありますが、箱全体だと材料費がかかさむものの、バッフル板だけの使用であればそれほど高額ではありません。
でも今回はそれはまたのお楽しみにします。
という事で、近所のホームセンターへ板材の買出しに出かけてみました。
自作派の方によく利用されるラワン合板やシナ合板も考えましたが、それではありきたりでつまらない話です。
コスト優先でMDF材も候補になりましたが、音質との兼ね合いでコストパフォーマンスは高いものの、それでもちょっと面白くありませんね。
見た目の綺麗さでパイン集積材や竹の集積材もいいとは思ったのですが、どうせならマニアが敬遠する材質を使用してみようと思ったのです。
そこで目に入ったのが、なんだかわけのわからない集積材です。
バルサほどではありませんが、非常に軽く柔らかめの材質です。
高硬度、高密度 高比重の三高の材質を望むマニアが多い中、あえて軟質、低密度 低比重のへっぽこ木材を使用してみる事にしました。
どのような材質かといえば、通販などで売っている安物の出来の悪い桐タンスに使われているような材質といえばお分かりでしょうか。

今まで段ボール箱で鳴らしてきた経験があるため、こんな低比重な軟質な材料でも十分勝算があっての話です。
それにこのくらい大きなハンデを与えないと、世の中にある高級ブランドのシステムより良く鳴ってしまいますから・・・
という事で今回はここまで。
次回はいよいよ完成風景についてご報告いたしますね。
PR
- トラックバックURLはこちら


